なぜだかわからないけど、おちこんでいる人からおちこんだ電話がかかってくることが多い。家に居てもあまり電話を取らないが(用があるのにつながらなかった人、御免なさい)、その種の電話は、なんとしても出なければならないと思わせるような有無をいわせない切実な鳴り方をする。で、出てみると、しばらく疎遠になっていた知人が、うまくいかない仕事や家族の確執や離婚問題や「誰かの声が聴きたくて」というようなことを話しだす。相手の細かい事情もわからないし、それ以前に社会の常識に疎いところがあるので、私の受答えは「そうなんだあ。大変だね。でも、自分を大切に生きて行けるといいよね」というあまりにも現実的な効力の無いものになる。それでも数人の知人が一定の期間を置いて〝電話〟をかけてくる。彼等とは電話でしか接点がないから、わたしは悩みという局面でしか彼等を知らないし、彼等は悩み事の聞き手としてのわたししか知らない。
幼稚園に上がった冬、女の子の間できつねのえりまきが大流行した。当時は動物の毛皮に対する抵抗感がわりと少なく、大人のひとのコンサバティブなファッションとして本物の狐をそのまま使ったえりまきが流行っていた。おしゃまな女の子たちのきつねのえりまきは、大人物の縮小コピーよろしくリアルにきつねをかたどったもので、うさぎの毛皮で出来ていた。口の部分がクリップになっていて、ぱくぱく動かしておしゃべりさせたり、それは、冬になれば再会する仲良しの縫いぐるみでもあった。独りぼっちの時や所在ない時には、彼女に手や頬で触れるのが冬のわたしの自然な動作だった。毎年寒くなると、どこにしまったっけ、無くしてしまったかも、という思いに駆られて行李を開ける。セーターやウールのスカートの間にひっそりと落ち着いている彼女をみつけてほっとする。柔らかいうさぎの毛皮に触れていると、無条件に心が落ち着いた。悲しいときも、べつに悲しくなんかないときも。
こんなことを30年以上繰り返しているうちに、いつのまにかそれがきつねの形をしていることは意識からこぼれ落ち、さらに、実際にうさぎの毛皮を頬摺りすることさえ必要でなくなった。呼ばれるまで行李のなかでひっそりと待ち続ける彼女の居住まいと、何もかも包み込んでくれる柔らかな感触を思い出すだけで満たされた。やがて、想像の中でうさぎのえりまきはじっとうずくまるほんもののうさぎの姿を形成した。冬だけでなく、一年中いつでもそこにうさぎがいる。こころを静かにしたいとき、うさぎのことを思えばいい。この地上のどこかに、あんなにおとなしくて柔らかい生きものが黙々と生きている、そのことをかんがえる。そうすると、晴れていても雨が降っても、自分のこころのある場所にしっかり立っていられればだいじょうぶ、そんな気持ちになれる。
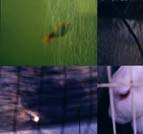

先日、1年ぶりの知人から〝電話〟があった。暗い空気。そのひとの悩みは一年前と何も変らず、変われないからこそわたしに電話をしてくるのかもしれない。人はなぜ、同じところを回り続けてしまうんだろう。つらい。誰がどんな言葉で慰めたって結局は自分で行動するしかない。自分が動かなければ、変化しなければ、何も変わらない。そんなことわかっていて、さらにどうしようもないことなのかもしれない。あのひとにも、なにかうさぎのようなものがいたらいいのに。うさぎは、たとえば円の中心。中心をしっかり押さえておけば強く引っ張って遠くに行っても、だいじょうぶ。中心があれば迷子にはならない。もしなったとしても、また自分の場所に新しく戻ってこれる。おそらく。たぶん。きっと。
ひとりひとりにじぶんのうさぎを。にんげんにはどうしようもないこともうさぎなら。